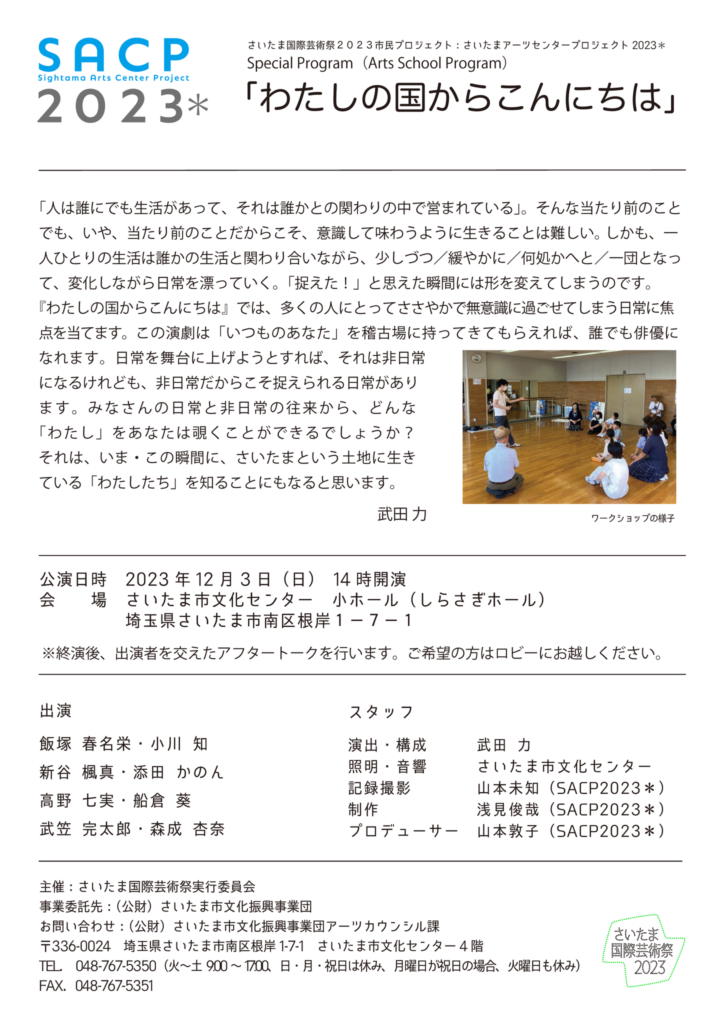「生きにくさはいつの世も」かもしれませんが、なにかが表面化すれば一方的に叩かれる世知辛い世の中になったなあと個人的には感じます。匿名による無数の書き込みがひとつの方向を示すように、その行動の根源には「本来こうあるべきだ」という変革への意識と同時に、正しさによる同調圧力が強く働いているように思えます。もちろん、社会が良いほうに変わっていくならば、それに越したことはないのですが、その際に必須であるはずの「目指したい社会とはなにか」といった議論は、「こんなこと言ったら自分も叩かれるかも」という恐怖心の下で、より成り立ちにくくなったように思えます。いずれにせよ、誰かを虐げることによって成り立つ「良さ」であってはならないと思います。たとえ、その人が加害者であっても、同時にまた被害者である側面にも視野を拡げることが、「目指したい社会」を多角的に考えることに繋がるのではないでしょうか?そんなことを思いながら、今年度「得体の知れないアートイベントをつくってみる」というプロジェクトを、「いしばしコモンズ」という大阪の石橋商店街に位置する古民家で始めました。近視眼に過ぎるいまの社会から一歩引いて、コモンズという共有地で安心して意見を述べ合ったり、一緒に物事を考えるプロジェクトです。そのメンバーが各々アートを用いた対話の場を開きます。テーマはさまざまですが、いずれもいまの社会を生きる一人ひとりが紡ぎ出した企画です。冒頭に記したステイトメントと比べて、とても緩いイベントになることは間違いないと思うのですが、笑。よかったら24日、いしばしコモンズへお越しください。
+++イベント概要+++
「得体の知れないアートイベントをつくってみる」発表会
発表者|菱田 伊駒、小林 真実、中村 太一
観察者|石田 絵里香
並走者(司会)|武田 力
場所:いしばしコモンズ
大阪府池田市石橋1丁目11-7 https://goo.gl/maps/zfxVcANLdv8daCwM6
日時:2024年3月24日(日)14:00~17:00
入場:無料(会の途中での入退場もご自由にどうぞ)
予約:不要(どなたでもどうぞ)
★24日の午前中に、同じ場所にて開催★
いしばしとボリビアをカレーでつなぐ
「チョリータカリー」
3月24日(日)11:00~13:00
https://fb.me/e/5wN0Jnj0V
こちらもぜひご参加ください!
+++これまでに開催したイベント+++
いしばしコモンズ シーズン1「で、結局アートってなんなんっすかね?」「得体の知れない箱を神輿に担ぎ上げるーいしばしコモンズ立ち上げの胴上げに代えてー」
https://www.facebook.com/events/596356949296583「アートで響くアジアを聞いてみようーいしばしコモンズ立ち上げの謝辞に代えてー」
https://www.facebook.com/events/615762297178190「家のミシンを持ち出して、得体の知れない箱をブルーシートで覆ってみるーいしばしコモンズ立ち上げの歓談に代えてー」
https://www.facebook.com/events/827611939057620「家の体重計を持ち出して、得体の知れない箱の重さをみんなで測ってみようーいしばしコモンズ立ち上げの祝辞に代えてー」
https://www.facebook.com/events/758933699266963
+++問い合わせ先+++
こちらのWebサイトの問い合わせよりお寄せください。
主催:いしばしコモンズ、助成:公益財団法人 芳泉文化財団